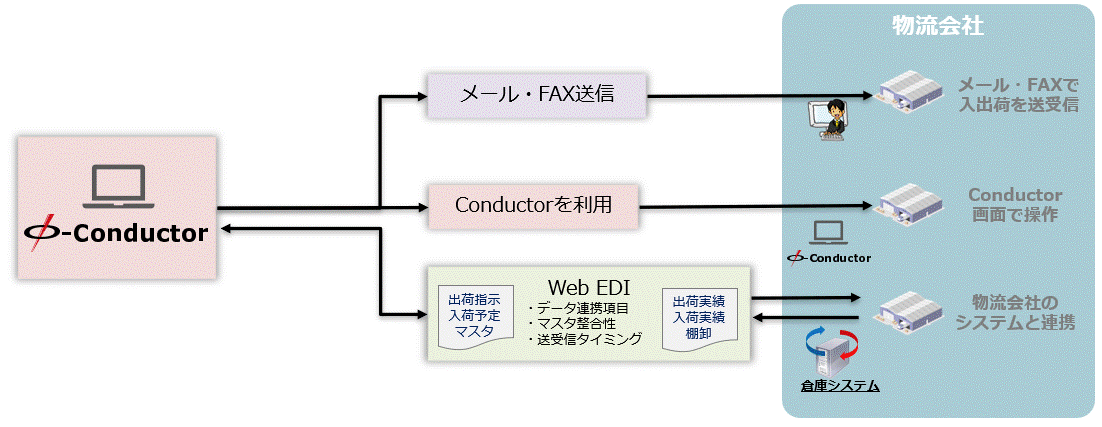倉庫業務支援
倉庫での入出荷指示の出力から入出荷実績の入力等、倉庫業務機能を用意し、φ-Conductor単体で倉庫オペレーションまでサポートしています。
すでに倉庫システムをお持ちであったり、外部委託倉庫を利用し、その倉庫会社で倉庫システムをお持ちの場合があります。このような場合、それら倉庫システムと連携する必要がありますが、φ-Conductorでは、倉庫システムと連携するための標準インタフェースを用意しています。
倉庫システム連携において、様々なパターンの連携がありますので、お客様の運用に適した連携を提案します。